中学地理「テストでよく出る一問一答」定期テスト対策です。
テストでよく出る一問一答(中学地理)
| 地図・地球儀 | 20題 |
| 世界地理 | 16題 |
| 日本地理 | 25題 |
地図・地球儀の一問一答
(1)世界で最も面積の大きな国はどこか答えなさい。
(2)世界で最も面積の小さい国はどこか答えなさい。
(3)地球の中心から見た地表の南北の角度を何と言うか。
(4)中心からの距離と方位が正しい地図は何に使われることが多いか答えなさい。
(5)日本の領域は何に基づいて定められているか。
(6)水産資源や鉱産資源を沿岸国が自由に利用することができる水域を何と言うか答えなさい。
(7)インドネシアは何と呼ばれる緯線の周辺にあるか答えなさい。
(8)ユーラシア大陸北部に広がる寒さの厳しい地域を何と言うか答えなさい。
(9)アンデス山脈で盛んに飼育されている家畜はアルパカと何か。
(10)アンデス山脈で行われているリャマやアルパカを放し飼いにする農業を何と言うか。
(11)ベトナムで食べられベトナムで食べられている米で作った麺類を何て言うか。
(12)イタリアで食べられている小麦粉から作ったスパゲッティ、マカロニなどを総称して何と言うか。
(13)アジアの中央部にそびえる標高8000m超える山脈は何か。
(14)モンゴルやアラビア半島など乾燥した地域で行われる国を何と言うか。
(15)太陽光や風力地熱などのような、枯渇することがなく温室効果ガスを放出しないエネルギーを何と言うか。
(16)韓国で使われてる独自の文字を何と言うか。
(17)東南アジアで天然ゴムやアブラヤシなどを栽培する大農園を何と言うか。
(18)デカン高原で栽培されている作物は何か。
(19)インドで長く続いていた身分制度は何て言うか。
(20)産油国が結成し、原油価格を設定して世界に大きな影響をしている組織を何と言うか。略称で書きなさい。
(1)ロシア
(2)バチカン市国
(3)緯度
(4)航空図
(5)国際法
(6)排他的経済水域
(7)赤道
(8)シべリア
(9)リャマ
(10)放牧
(11)フォー
(12)パスタ
(13)ヒマラヤ山脈
(14)遊牧
(15)再生可能エネルギー
(16)ハングル
(17)プランテーション
(18)綿花
(19)カースト
(20)OPEC
世界地理の一問一答
(1)複数の国を通って流れるライン川やドナウ川のような河川を何と言うか。
(2)ヨーロッパ北部に見られる氷河によって削られた地形を何と言うか。
(3)ヨーロッパの大西洋岸を北上する海流を何と言うか。
(4)地中海沿岸で行われている乾燥に強いオリーブやぶどう小麦を栽培する農業を何と言うか。
(5)小麦やライ麦などの穀物栽培と家畜の飼育を組み合わせた農業を何と言うか。
(6)ヨーロッパヨーロッパ北部やアルプスの周辺地域で冷涼な気候を生かして行われる農業を何というか。
(7)南アフリカ共和国で1990年代初めまで行われてきた人種隔離政策を何と言うか。
(8)コートジボワールやガーナで盛んに生産されている農産物は何か。
(9)アフリカ大陸にある豊富にある携帯電話やコンピューターなどに使われる希少な金属を何と言うか。
(10)アフリカなど技術支援や開発支援を行っている非政府組織はアルファベット3文字で何と呼ばれるか。
(11)北アメリカ大陸の先住民は何と言うか。
(12)穀物を取り扱う企業で世界の市場の影響を与えている大企業を何と言うか。
(13)五大湖周辺に古くからの自動車工業が盛んな都市はどこか。
(14)1970年代以降に工業が発達したアメリカ合衆国の北緯37度以南の新しい工業地域を何と言うか。
(15)サンフランシスコ郊外にコンピューター関連産業の中心地を何ト言うか。
(16)世界各地に生産販売拠点を持つ企業を何と言うか。
(1)国際河川
(2)偏西風
(3)北大西洋海流
(4)地中海式農業
(5)混合農業
(6)酪農
(7)アパルトヘイト
(8)カカオ豆
(9)レアメタル
(10)NGO
(11)ネイティブアメリカン
(12)穀物メジャー
(13)デトロイト
(14)サンベルト
(15)シリコンバレー
(16)多国籍企業
日本地理の一問一答
(1)ペルシャ湾岸に集中して分布している資源は何ですか。
(2)石油、石炭などをまとめて何燃料と読んでますか。
(3)主な工業地帯地域が集中している太平洋側沿岸に帯のように連なる地域を何と言いますか。
(4)商業やサービス業などのを何産業と言いますか第何次産業と言いますが。
(5)重量の重い機械類や燃料原料の移動に使われる輸送手段は何ですか。
(6)原料を輸入しそれを工業製品として加工し輸出しする貿易を何と言いますか。
(7)貿易摩擦などの解消などを目的とし設立された国際貿易機関の略称答えなさい。
(8)九州南部に広がる火山の噴出物が堆積した台地を何と言いますか。
(9)かつて沖縄県で栄えた王国を何と言いますか。
(10)土地がやせている北九州地方南部は畑作と何が盛んですか。
(11)下関と北九州市の間にある海峡を何と言いますか。
(12)原子爆弾が落とされた広島市にある負の遺産として世界文化遺産に登録された遺跡を何と言いますか。
(13)海上交通の便が良いことを貼って発達した倉敷、福山などを含む工業地域を何と言いますか。
(14)大阪を中心とする人やモノの動きで深く繋がってる地域を何と呼びますか。
(15)淡路島などで盛んに行われている大都市向けの野菜などを生産する農業を何と言いますか。
(16)大阪湾に沿って作られた液晶パネル、太陽電池などを生産する地域を何と呼んでいますか。
(17)飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈をまとめてヨーロッパの地名をとって何と言いますか。
(18)静岡県の太平洋側に発達している楽器やオートバイ製紙工業が盛んな工業地域を何と言いますか。
(19)流域面積が日本一の河川を何と言いますか。
(20)都市部の気温が周辺部より高くなる現象を何と言いますか。
(21)成田国際空港のある都道府県名を書きなさい。
(22)東北地方で伝統的に作られた南部鉄器や会津焼きは何と呼ばれていますか。
(23)北海道の先住民を何と言いますか。
(24)北海道地方にある自然豊かな自然環境が認められ世界自然遺産に登録されたのはどこですか。
(25)国土地理院が発行している土地の様子を詳しく記した地図を何と言いますか。
(1)石油
(2)化石燃料
(3)太平洋ベルト
(4)第3次産業
(5)海上輸送
(6)加工貿易
(7)WTO
(8)シラス台地
(9)琉球王国
(10)畜産
(11)関門海峡
(12)原爆ドーム
(13)瀬戸内工業地域
(14)大阪大都市圏
(15)近郊農業
(16)パネルベイ
(17)日本アルプス
(18)東海工業地域
(19)利根川
(20)ヒートアイランド現象
(21)千葉県
(22)伝統的工芸品
(23)アイヌ
(24)知床
(25)地形図
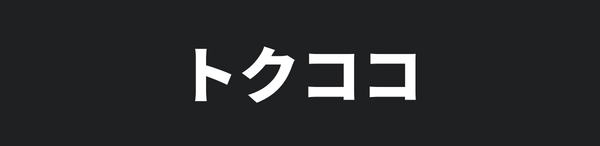

コメント