高校入試対策理科「頻出の理科の記述問題演習」です。
頻出の理科の記述問題演習
・中1理科の記述問題
・中2理科の記述問題
・中3理科の記述問題
・無学年の記述問題
に分けて構成しています。
中1理科の記述問題
1.身近な生物の観察の記述問題
ステージ上下式顕微鏡でピントを合わせるとき、接眼レンズをのぞきながら、対物レンズとプレパラートを近づけてはいけない。これは、どのようなことを防ぐためか、簡潔に書きなさい。
2.種子をつくる植物の記述問題
(1)単子葉類と双子葉類は、それぞれ葉脈がどのように通っているか、簡潔に書きなさい。
(2)サクラでは受粉が起こった後、胚珠と子房はそれぞれ何になるか簡潔に書きなさい。
(1)単子葉類は平行に通り、双子葉類は、網目状に通る。
(2)胚珠は種子になり、子房は果実になる
3.植物の分類の記述問題
シダ植物とコケ植物の体のつくりのちがいを「葉、茎、根」という語句を用いて、簡潔に書きなさい。
4.動物のなかまの記述問題
(1)両生類の呼吸のしかたを、子とおとなのちがいがわかるように、簡単に書け。
(2)節足動物のうち昆虫類に共通する特徴を体の分かれ方と足のつき方に着目して簡潔に記述しなさい。
(1)子はえらと皮ふ、おとなは肺ち皮ふで呼吸する。
(2)体が頭部、胸部、腹部に分かれ、6本のあしが胸部についている
5.いろいろな物質の記述問題
ガスバーナーで、赤色の炎が適正な青色の炎にするには、どのような操作をすればよいか。「ガス調節ねじ」、「空気調節ねじ」という語句を用いて、簡潔に書きなさい。
6.気体の発生と性質の記述問題
(1)試験管に集めた気体のにおいを確かめるときは保護眼鏡をして、どのようにするのがよいか、簡潔に書きなさい。
(2)水上置換法で気体を集めるときは、はじめに出てくる気体をしばらく空気中に出してから集める。はじめに出てくる気体は集めない理由を簡潔に記述しなさい。
(1)手であおぐようにして、においを確かめる
(2)はじめに出てくる気体は実験器具の中にあった空気を含むから
7.物質の状態変化の記述問題
物質の状態が、液体から気体に変化すると、その質量と体積はどうなるか、簡潔に書きなさい。
8.水溶液の記述問題
物質が水に溶けると見えなくなる理由を、「物質の粒子」という語句を用いて簡潔に書きなさい。
9.光の性質の記述問題
反射の法則とはどのようなことか。「入射角」、「反射角」という語句を用いて簡潔に書け
10.音の性質の記述問題
雷が光ってからその音が聞こえるまでに時間がかかるのは光の速さと音の速さにどのように違いがあるからか簡潔に書きなさい
11.火山の記述問題
(1)溶岩や軽石の表面に見られる穴のでき方を「マグマが冷えるときに」という書き出しで、簡潔に書きなさい。
(2)無色鉱物には石英と長石があり、これらは形で区別することができる。石英と長石の形の特徴を簡潔に記述しなさい 。
(1)マグマが冷えるときに、気体成分が抜けた跡が残って穴になった
(2)石英は不規則な形で、長石は柱状、短冊状をしている
12.地震の記述問題
地震発生すると初めに初期微が起こり、後から主要動が起こるのはなぜか、その理由を、「P波」、「S波」、「発生する時刻」、「伝わる速さ」という語句を用いて簡潔に記述しなさい。
13.地層の記述問題
長い年月の間に海底の同じ場所に堆積するものが変わるため、色々な層が重なった地層ができる。同じ場所に堆積するものが変わる理由を長い「長い年月の間に」という書き出しで、簡潔に書きなさい
14.大地の変動の記述問題
海のプレートの移動を「海嶺」「海溝」という語句を用いて説明しなさい。
中2理科の記述問題
1.気体の集め方の記述問題
上方置換法の気体の集め方が適しているのはどのような性質を持つ気体ですか、「水」と「密度」という二つの語を用いて書きなさい。
2.状態変化の記述問題
エタノールと水の混合物の加熱では、試験管に溜まった気体には、水よりもエタノールが多く含まれていました。このような結果が得られた理由を書きなさい。
3.炭酸水素ナトリウム熱分解の記述問題
炭酸水素ナトリウムを加熱する実験で試験管の口を少し下向きにするのはなぜですか、簡潔に書きなさい。
4.炭酸水素ナトリウム熱分解の記述問題
炭酸水素ナトリウムを加熱する実験で石灰水に入れたゴム管の先には火を消す前に石灰水その中から取り出します・その理由を答えなさい。
5.水の電気分解の記述問題
水の電気分解の実験で純粋な水でなく水酸化ナトリウムを溶かした水を使うなぜですか簡潔に述べなさい。
6.炭酸水素ナトリウムの記述問題
炭酸水素ナトリウムはホットケーキを作る時に小麦粉に混ぜるベーキングパウダーの主な成分です。ベーキングパウダーを入れて作ったホットケーキがスポンジ状に膨らむのはなぜですか簡潔に述べなさい。
7.マグネシウムリボンとスチールウールを加熱する実験の記述問題
マグネシウムリボンとスチールウールを加熱する実験でマグネシウムリボンを加熱すると激しい光が発生します。このとき目を痛めるのを防ぐためにどうしますか述べなさい。
8.質量保存の法則の記述問題
スチールウールが燃えた後にできた物質の質量も入る前のスチールウールの質量と比べるとどうなっていますか。理由を含めて簡潔に書きなさい。
9.スチールウールを燃焼の記述問題
密閉した容器の中でスチールウールを燃焼させました。反応の前後で容器全体の質量はどうなりますか、その理由を含めて書きなさい。
10.細胞分裂の記述問題
根の先端近くに根毛が多数あるが、根毛があることで水や無機物を効率的に吸収することができます。それはなぜか簡潔に書きなさい。
11.茎や根のはたらきの記述問題
葉で作られたデンプンはどのようにして茎や根に運ばれますか。その物質が通る管の名前を用いて、簡潔に書きなさい。
【解答】 水に溶けやすい物質に変えられて師管を通って運ばれる
12.肺のはたらきの記述問題
ヒトの肺は肺胞が多数集まってできています。このことは気体を交換するのにどのようなことに役立っていますか、簡潔に書きなさい。
13.血液の成分の記述問題
血液が赤色に見えるのは赤血球に含まれているヘモグロビンという物質のためです。酸素はヘモグロビンと結ぶことによって全身に運ばれます。ヘモグロビンの酸素に対する性質について簡単に書きなさい。
14.電流の記述問題
電流計を電源に直接つないではいけません。その理由を簡単に書きなさい。
15.電圧と電流の関係の記述問題
電圧と流れる電流の関係を調べる実験を行う時、電源装置の電源プラグをコンセントに繋ぐ前に確認すべきことを二つ書きなさい。
16.発熱の記述問題
一つのテーブルタップに多くの電気器具をつないで使うと危険です。その理由を「電流」、「発熱」の語を用いて書きなさい。
17.天気の記述問題
晴れてる日の気温と湿度の変化にはどのような関係があると言えますか簡単に書きなさい。
18.放射冷却の記述問題
曇りの日の夜に放射冷却の現象が起こりにくい理由を書きなさい。
19.気圧計の記述問題
簡易真空容器の中の空気を抜いていくと気圧計と温度計の値はそれぞれどのように変化しますか簡単に書きなさい。
20.前線の記述問題
北半球の低気圧において道側にのびる前線と東側にのびる前線の移動の速さの違いについてそれぞれの前線の名称を用いて簡単に書きなさい。
中3理科の記述問題
次の問いに答えなさい。
1.熱伝導の記述問題
熱伝導とはどのような現象か簡単に書きなさい。
2.斜面を下る運動の記述問題
斜面の角度を大きくした場合、斜面上での小球の速さの増え方はどうなるか。小球の運動の向きに変わる力の大きさに注目して簡単に書きなさい。
3.生殖の記述問題
自家受粉とはどのような受粉か簡単に書きなさい。
4.動物の分類の記述問題
恒温動物とは、どのような動物か簡単に書きなさい。
5.細胞分裂の記述問題
ソラマメの根はどのように成長していくと言えるか。細胞の数と大きさに着目して簡潔に書きなさい。
6.相同器官の記述問題
相同器官とはどのようなことを示す証拠の一つか簡単に書きなさい。
7.燃料電池の記述問題
燃料電池の電池は自動車にも利用されガソリンを使って動く自動車と比べて環境に及ぼす悪影響が少ない、その理由を簡単に書きなさい。
8.水溶液の記述問題
硫酸に水酸化バリウム水溶液を加えた時、水溶液にある変化が見られる。それはどのような変化か、簡潔に書きなさい。
9.公転の記述問題
太陽が天球上を動くように見えるなぜか。「公転」という言葉を用いて簡単に書きなさい。
10.金星の記述問題
金星が真夜中に観察できないのなぜか。簡単に書きなさい。
11.太陽の日周運動の記述問題
太陽の日周運動の道筋が季節によって変わるのはなぜか。簡単に書きなさい。
12.月の記述問題
月食とはどのような現象か。「月」、「地球」という言葉を使って書きなさい。
13.太陽の黒点の記述問題
太陽の黒点が黒く見えるのなぜか、簡単に書きなさい。
14.天体望遠鏡の記述問題
天体望遠鏡を使って太陽を観察するとき、太陽を直接見ていけないのはなぜか。その理由を簡単に書きなさい。
15.金星の記述問題
金星は見かけの直径が大きく変わるのに対して、月が見かけの直径があまり変わらない。月の見かけの直径があまりわからない理由を、地球との距離に着目して簡単に書きなさい。
16.地球温暖化の記述問題
地球温暖化で海水面が上昇するのはなぜか、簡潔に書きなさい。
17.生物多様性の記述問題
指標生物の種類を調べることで、川の水の汚れの程度を知ることができるのはなぜか。その理由を簡単に書きなさい。
18.環境問題の記述問題
使用後のプラスチックが、自然界でマイクロプラスチックとなり環境への影響が心配されている。具体的にどのようなことが心配されているか一つ簡単に書きなさい
19.X線の記述問題
医療のX線撮影では、体の中の骨がはっきり映って見える。このことからX線の透過性の性質ついてどのようなことがわかりますか、簡潔に書きなさい。
高校入試よく出る理科の記述問題
【A】次の問いに答えなさい。
(1)水溶液から結晶を得る方法として、水溶液を冷やすほかにどのような方法があるか、書きなさい。
(2)花火が開いて音が聞こえるまで、少し時間がかかるのはなぜか。
(3)被子植物の特徴を「子房」「胚珠」の語を用いて説明せよ。
(4)シジミは、示相化石の1つである。示相化石とはどんな化石か、説明せよ。
(5)炭酸水素ナトリウムの熱分解の実験で、試験管の口を少し下げて加熱するのはなぜか、理由を書け。
(6)マグネシウムリボンを燃焼させたとき、燃焼後に残った物質の質量をはかると、燃焼前のマグネシウムの質量よりも大きくなる。その理由を書け。
(7)ハ虫類の前あしや鳥類のつばさとヒトの腕などは、相同器官と呼ばれている。相同器官とはどんな器官か、説明せよ。
(8)柔毛のような突起がたくさんあると、物質の吸収の効率がよくなる。その理由を書け。
(9)ソラマメの根の細胞はどのような変化によってのびていくか、説明せよ。
(10)金星は、地球上では真夜中に観察することができない。その理由を「公転」の語句を使って書け。
【B】次の問いに答えなさい。
(1)サクラの花粉がおもに虫によって運ばれるのに対して、マツの花粉はおもにどのように運ばれるか。
(2)果実をつくるか、つくらないかという点で、裸子植物と被子植物には違いがみられる。このことについて、裸子植物と被子植物のそれぞれの花のつくりにおける特徴にふれながら、どちらの植物が果実をつくるかを説明せよ。
(3)単子葉類の葉脈と根のつくりの特徴を簡潔に書け。
(4)葉の枚数と大きさがほぼ同じ枝をそれぞれ試験管A、Bにさし、Aの葉の表側に、Bは葉の裏側にワセリンを塗って、試験管に少量の油を注ぎ、3時間放置して、水の減少量を調べた。この実験で、試験管に少量の油を注いだ理由を簡潔に書け。
(5)葉の枚数と大きさがほぼ同じ枝をそれぞれ試験管A、Bにさし、Aの葉の表側に、Bは葉の裏側にワセリンを塗って、試験管に少量の油を注ぎ、3時間放置して、水の減少量を調べた。その結果、Aの方がBよりも水の減少量が多かった。このことからわかることを、「気孔」という語句を用いて、簡潔に書け。
(6)双子葉類は、花びら(花弁)のつくりかから、合弁花類と離弁花類に分類できます。それぞれの特徴を、「花びら」という語句を用いい、「ヒマワリ」「サクラ」がどちらに分類されるも明らかにして簡潔に書け。
(7)シダ植物と比べて、コケ植物の体のつくりには、どのような特徴があるか簡潔に書け。
(8)葉の光合成を調べる実験では、アルミニウムはくでおおった部分とふの部分がヨウ素液につけても、青紫色にならなかったのは、光合成が行われなかったからである。光合成が行われなかった理由をそれぞれ簡潔に書け。
(9)葉の光合成を調べる実験では、うすいヨウ素液につける前にエタノールに入れるますが、何のためか簡潔に書け。
(10)葉から水が蒸散することは、植物にとって、どのようなことに役に立っているか。
(11)植物の根の先端付近には、毛のように細い根毛がある。このようなつくりはどのように役に立つか、簡潔に書け。
【C】次の問いに答えなさい。
(1)デンプン溶液5cm3を入れた試験管A,B,C,Dを用意し、AとBには水でうすめた唾液を、CとDには水をそれぞれ2cm3加えた。次に、それぞれA~Dの試験管を40℃の湯に入れ、10分間そのままにしておいた。その後、試験管AとCにはヨウ素液を加え、試験管BとDには、ベネジクト液を加えてガスバーナーで加熱して、色の変化を記録した。この結果から、だ液にはデンプンを消化するはたらきがあることがわかる。試験管AとCの結果からわかることと試験管BとDの結果からわかることをそれぞれ簡潔に書け。
(2)細胞には、組織液によって運ばれた養分からエネルギーを取り出すしくみがある。そのしくみは、どのようなものか。「酸素」「二酸化炭素」「水」という語句を用いて、簡潔に書け。
(3)明るいところからうす暗いところへ移動すると、ひとみの大きさはどうなるか。また、ひとみが大きくなったり、小さくなったりすることは、どのような役割を果たしているか。
(4)心房と心室、心室と動脈の境にはそれぞれ弁がついているのは、なぜか簡潔に書け。
(5)ヘモグロビンは肺で酸素と結びつき、体の各部の細胞まで運ぶ。細胞への酸素の受け渡しが可能なのはヘモグロビンがどのような性質をもっているからか、簡潔に書け。
(6)小腸の内壁には、たくさんの柔毛がある。これは養分の吸収にどのように役に立つか、簡潔に書け。
(7)肺の内部には、小さな袋状の肺胞からできている。肺のこのようなつくりはどのように役に立つか、簡潔に書け。
(8)ハチュウ類の体温と卵の特徴を簡潔に書け。
(9)草食動物の門歯と臼歯は、どのようなことに適しているのか、簡潔に書け。
【D】次の問いに答えなさい。
(1)タマネギの根の先端部分を使って、細胞分裂のようすを顕微鏡で観察するとき、顕微鏡で観察するまえに、約60℃の湯であたためたうすい塩酸に数分間入れる理由を「細胞どうし」という語を用いて、簡潔に書け。
(2)タマネギの根の先端部分を使って、細胞分裂のようすを顕微鏡で観察するとき、切片に酢酸オルセイン液をたらして観察する理由を簡潔に書け。
(3)タマネギの根の先端部分を使って、細胞分裂のようすを顕微鏡で観察するとき、根の先端部分を用いる理由を簡潔に書け。
(4)タマネギの根は、細胞のどうのような変化によって成長するか。体細胞分裂の結果をふくめて、簡潔に書け。
(5)純系の遺伝とはどういう系統か簡潔に書け。
(6)デンプンをふくんだ寒天液の入った3つのペトリ皿を用意する。Aには林の中の土をそのまま入れ、Bには林の中の土を十分に焼いてから入れ、Cには何もいれなかった。フタをして2~3日放置した後、ヨウ素液を加えて反応を確かめた。このとき、フタをするのはなぜか簡潔に書け。
(7)(6)のとき、Aは、ヨウ素液が反応しなかった。それはなぜか簡潔に書け。
(8)食物連鎖において植物は、生産者であるが、生産者のはたらきを簡潔に書け。
(9)食物連鎖において菌類、細菌類は、分解者であるが、なぜ分解者と言われるのか簡潔に書け。
(10)受精卵が細胞分裂をして胚になりさらに細胞分裂を繰り返して固体となる過程を発生といいますが、カエルの場合、胚がどういう行動をしはじめるとおたまじゃくしと呼ばれるのか簡潔に書け。
高校入試よく出る理科の記述問題(解答)
【A】の解答
(1)加熱して水を蒸発させる。
(2)音の伝わる速さは、光が進む速さよりも遅いため。
(3)胚珠が子房に包まれている花を咲かせる。
(4)地層が堆積した当時の自然環境がわかる化石。
(5)生じた液体(水)が、底の方へ流れるのを防ぐため。(➡液体が加熱している部分にふれると、試験管が割れる危険がある。)
(6)化合した酸素の分だけ、質量が大きくなるから。
(7)形やはたらきがちがっていても、もとは同じ器官であったもの。
(8)表面積が広くなり、物質との接触面積が広がるから。
(9)細胞分裂で、細胞数が増え、それらがもとの大きさに成長することによって根が伸びる。
(10)地球よりも太陽に近いところを公転しているから。
【B】の解答
(1)風によって運ばれる。
(2)裸子植物は、子房がなく胚珠がむきだしであるが、被子植物の胚珠は子房に包まれている。果実は、子房が成長してできているので、果実がつくられるのは被子植物である。
(3)葉脈は平行脈で、根はひげ根である。
(4)水面からの水の蒸発を防ぐため。
(5)気孔は葉の裏側に多い。
(6)合弁花類は、ヒマワリのように花びらが1つにくっついている植物で、離弁花類は、サクラのように花びらが1つ1つ離れている植物
(7)維管束がなく、葉、茎、根の区別がない。
(8)アルミニウムはくでおおった部分では、光があたらないから。ふの部分では、葉緑体がないから。
(9)脱色するため。
(10)根からの水や養分の吸い上げに役立つ。
(11)表面積を広げ、水や水に溶けた養分の吸収の効率を上げるのに役立つ。
【C】の解答
(1)試験管AとCの結果からは、だ液によってデンプンがなくなること。試験管BとDの結果からは、だ液によって、デンプンが分解され糖ができた。
(2)酸素を使って、養分を二酸化炭素と水に分化し、このときエネルギーを取り出す。
(3)ひとみは大きくなる。目に入る光の量を調節する役割を果たす。
(4)血液が逆流するのを防ぐため。
(5)酸素が少ないところでは結びついた酸素を放す性質をもっているから。
(6)表面積を広げ、効率よく養分を吸収するのに役立つ。
(7)表面積を広げ、効率よく酸素を取り入れるのに役立つ。
(8)体温は一定でなく、卵はかたい殻でおおわれている。
(9)葉をちぎったりすりつぶしたりすることに適している
【D】の解答
(1)細胞どうしを離れやすくするため(細胞どうしの結合を切るため)
(2)細胞を見やすくするため(核を赤色に染めるため)
(3)根の先端付近では、さかんに細胞分裂が行われるから。
(4)細胞分裂によって、細胞の数がふえ、それぞれの細胞が大きくなる。
(5)親、子、孫と代々(代を重ねても)同じ形質が現れる系統
(6)空気中の分解者がデンプンを分解してしまうのを防ぐため。
(7)土の中にいた分解者によってデンプンが分解されたから。
(8)光合成によって無機物から有機物を作り出す。
(9)有機物を無機物に分解するから
(10)自分で食物をとる
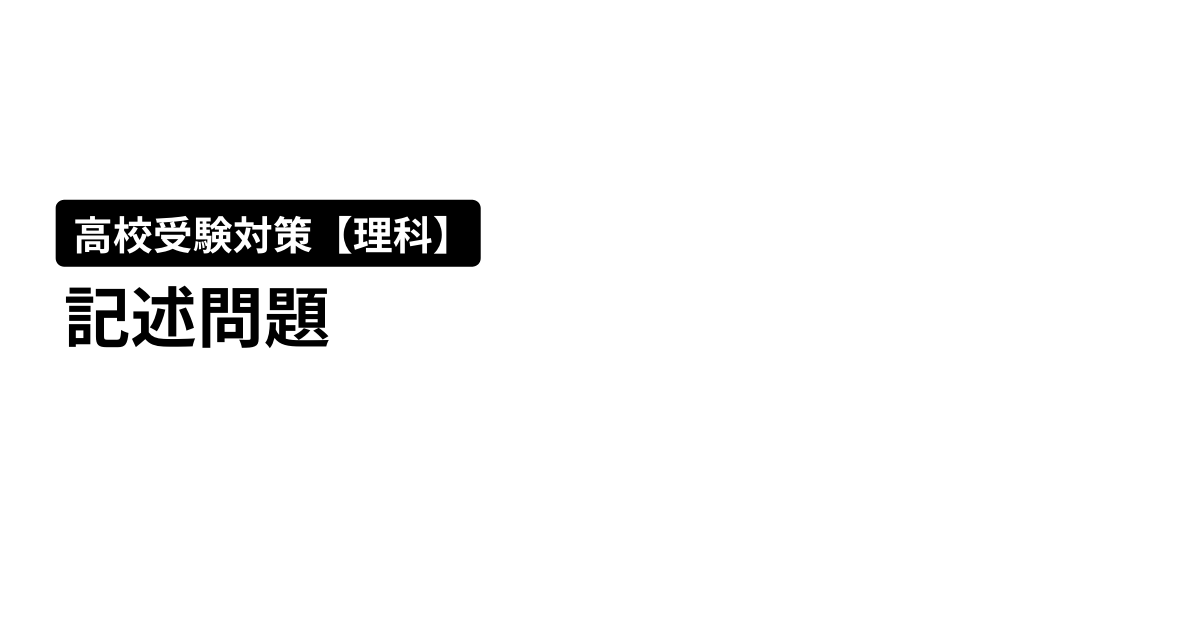
コメント